認知心理学(知覚や学習、記憶、言語、思考などを司る人間の認知プロセスを記述、説明、予測する学問)に基づいた研究成果(メニュー「指導資料」)を取り入れ、これに職人的な独自の工夫を加え、良質で安価な個別指導で、伸ばします。 改訂20250201

- 北摂英数学院の特徴
- 目次
- ●1 指導ステップ「説明→演習→進級テスト」→宿題 によるキッチリ指導
- ●2 速読重視の英語指導(中学生)
- ●3 自学能力を高める徹底した反復指導
- ●4 充実した中間・期末テスト(中学生)
- ●5 毎回の指導報告と年2回の定期保護者面談
- ●6 低月謝による圧倒的な指導回数・時間数・宿題チェック
- ●7 志望高と生徒の両方に合わせた「私立・県立高入試対策」 。無理・無駄のない「中学入試対策」。
- ●8 電子教育書籍を多数著作の指導経験豊かな塾長
- ●9 理系コース新設 ! 将来を定めた指導へ !
- ●10 学習障がい生の指導
●11 効率的な学習法(特に暗記術)の指導
●12 英単語の暗記指導法 - ●1 ①指導ステップ「②説明→③演習→④進級テスト」→⑤宿題 によるキッチリ指導
①指導ステップの細分化
当塾では、中1数学「方程式」の計算分野を11ステップ、文章題分野を15ステップに細分化しています。そのステップごとに、「説明→演習→進級テスト 」 によるキッチリ指導をしています。もし、進級テストで不合格になったときの説明範囲は、そのステップの学習範囲に限定されます。これにより、短時間で再説明をして、待たすことなく他の生徒も同時に指導できるのです。
一方、進学塾や学校での中間・期末テストのように、単元ごとにテストをする場合はどうでしょうか。もし、方程式の単元テストで不合格になったときの説明範囲はその単元全部に広がります。説明時間が大幅に増え、2時間を超えることもあるでしょう。その生徒につきっきりになって、他の生徒の指導どころではなくなります。何よりも、分らないまま、方程式の授業をずーっと我慢して聞いていた生徒がかわいそうです。月謝が無駄です。月謝を出してわが子をダメにする様なものです。
「計算分野を11ステップ」と前述しましたが、上位生の場合は、新幹線「のぞみ」が停車駅を少なくして高速走行するように、11ステップを3ステップにまとめて短時間指導し、浮いた時間を応用問題の指導に使うというように、学力差に対応しています。 結果として、下位生を伸ばすための「細かいステップ指導法」が中・上位生を一気に伸ばすことができ、北三・高専合格へと導くことができるのです。
また、どんなによくできる生徒でも、苦手分野が必ずあるものです。「指導ステップの細分化」は、そんな時の指導にも使えます。 
「学習進度表」の有効活用:指導月日、進級テスト成績、宿題内容と宿題月日を教科ごとに記入する用紙が学習進度表ですす。病院のカルテのようなものです。
一度合格しても時間が経つと忘れますから、前回の指導月日から2週間以内に再テストをして忘却を防ぐことができます。また、進級テストに多くの生徒が不合格になるときは、説明の仕方を分かりやすく変えるとか、類題演習数を増やすとか、指導のステップを細かく設定するとか、このように指導法の向上に役立てることができます。
②説明の多様化
説明は、短時間で、わかりやすくを心がけています。
1,数学の計算方法の指導では、説明文と数式の対応部分を色鉛筆の同色で表示して、分かりやすくしています。数学の文章題では、拡大したプリントに、線分図などの図解を色塗りして、一目で分かるようにしています。また、近年、空間認識能力(物体の位置・方向を、すばやく正確に把握、認識する能力。3歳から5歳の幼児期に特に伸びるといわれています)が劣ってきたという学力テスト結果が報告されています。このため、立体模型を作って、空間図形を指導しています。数学の立体模型作り
2,理科の電磁気は、簡単な実験で現象を説明。生徒自身にも実験させています。化学は、分子模型を使って説明します。ただし、時間のかかる反応実験はしません。火を使う実験はしません。
3,理・社はYouTubeを視聴させています。さらに、社会の地理・歴史は学習漫画を読ませます。
4,英語は、単語・教科書音読・文法はICレコ―音声を使っています。再生速度が変えられるので、分かりにくい時はゆっくりと聞けます。発音は、口の模型を作って、日本語にないr,th,vの指導をしています。
5,国語では、古文、故事成語、漢文、四字熟語、熟語、ことわざの指導には、学習漫画を使います。
6,「分かる」と「覚えやすい」との間には密接な関係があります。覚えにくいものは分らないものです。そのために、全教科に覚えやすい、語呂合わせを多用しています。
③多量の演習
解法をしっかり習得させるため、多量の演習問題をさせます。説明を繰り返すよりも、問題演習が成績アップに有効、との論文に基づいています。
④進級テスト
せっかく多量の演習をさせても、手抜きする生徒がいます。それを防止するため、緊張感を与える進級テストをします。この成績は、毎回保護者に提出しています。
⑤宿題
エビングハウスの忘却曲線「人は1日経つと74%忘れる」との論文に基づいて、授業と同じくらい重要な宿題は必ず出します。宿題内容は合格した進級テストの範囲から出すので、生徒は自力でできます。次回の授業日に宿題ノートを調べ、宿題達成度を記録し、毎回保護者に提出します。✕が多い生徒には宿題のやり直しをさせます。
最近は、問題集の解答を生徒に渡しています。理由は、これまで、宿題で間違った解法で誤答を量産する生徒がいたからです。この時、問題を解いて、すぐに手元の解答で答え合わせができたら、早く間違いが修正できて、学力アップにつながるはずです。
「解答の丸写しをしても、塾で宿題範囲のテストをするので、ばれるぞ」と、くぎを刺しています。
授業中は「~さん、質問ありませんか? 進級テストできますか? 出来ましたか?」と一人6回以上の「声かけ」をして、おとなしい生徒でも気軽に質問できる環境にしています。AIの時代だからこそ、人と人との会話の時間を確保しています。
- ⑥公文式と当塾の指導法の違い
下位生の場合
- 公文式さんは、「自分のペースで進み学びの習慣がつく楽にできるレベルから始まって、少しずつ難しい問題に挑戦していく」指導法です。一方、当塾は「学校の授業を生かせるようにするために、なんとか学校の進度に合わせる」指導法です。
なぜ、当塾は「学校の進度に合わせようとするのか」を説明しましょう。
中1数学の1年間の標準授業コマ数(1コマは50分)は140コマです。50分×140コマ=約117時間が、1年間の数学の総授業時間となります(これは中1英語も同じ)。
- せっかく学校に行っても、授業が全然分からなければ、ただボーッとしているだけですから、授業が身に付きません。宿題が出されても、白紙を提出すると、先生やお母さんから叱られますから、解いたふりをして、「いい加減なこと」を解答欄に書きます。当然、宿題も身に付きません。まるで、穴の開いたバケツに水を入れているようなものです(下図)。上から授業が注水されて、下の穴から漏れ出ています。
- この身につかなかった時間を、塾で補うとしたら、塾の費用を1時間700円とすると、700円×117時間=81,900円かかり、月に12時間習うとすると、117÷12=約10か月かかることになります。これはあまりにも、もったいない。だから、当塾は「学校の進度に合わせようとする」のです。直近の中間・期末テストの成績を少しでも上げて、自信を持たせることを優先するからです。
しかし、学校の進度に合わせる指導とつまずき個所にもどる指導という2重の負荷は、下位生にとっては酷な場合があります。学校の授業のない、春・夏・冬の長期の休み中が最適です。
- もう一つ、学校に行っても授業が全然分からないことの弊害を言います。
「いい加減なこと」が時々正解になることです。まぐれの正解でも、生徒本人にとっては、色いろ考えた結果なのです。「分からなければ、自分でよく考えろ」と大人は言いますが、それを正直に実行した成果なのです。もちろん、なぜ正解なのか、なぜ間違いなのかは、生徒本人は理解できていませんが、空白の答案用紙を提出して、叱られるよりはずっとましです。
こうして、間違った解法を習得してしまいます。よく「つまずいたところに戻って指導すれば伸びる」と(実は私も)言いますが、半分は不正確です。ことわざに「病ヤマイは治るが癖クセは治らぬ(病気は治療次第で治るが、身についた癖を治すのは難しいということ)」があります。間違った解法を矯正するのに時間がかかることです。一時的に治ったとしても、再発します。定期的な確認のための検査が必要です。
- 具体的な下位生の指導例
- ➊授業の最初に「学校は今どこをしている」と聞き、学校の進度に合うように、この日の塾の指導内容を決めます。
- ➋数学の場合:計算分野は既習分野が分らないと、指導出来ませんが、基本的な計算問題だけを何とか解けるようにします。夏期講習などの長期の休み中に、つまずき個所まで戻って、計算分野の補習をします。一方、図形分野は範囲が狭いので前学年にもどりながらでも指導できるところがあります。確率・統計も同じです。
➌英語の場合:文章(文型・文法)は難しいので、英単語の発音と日本語の意味を覚えさせます。単語が分かれば、学校で、今、先生は教科書のどこを読んでいるかが分かります。授業が少し分かってきます。英文和訳が出来れば、長文読解もできるようになります。記号で答える問題の正答率も向上します。夏期講習などの長期の休み中に、つまずき個所まで戻って、大急ぎで文型・文法の補習をします。
➍他の教科も、学校進度に合わせて指導できる項目を優先的に指導します。
中・上位生の場合
学校の予習になるように指導します。発展問題も指導します。速く終われば、他の教科(国・理・社)をします。 - このページのトップに戻る
- ●2 速読重視の英語指導
英語の進級テストには、教科書本文の「時間制限付き(タイマー使用)の速読テスト」を課しています。教科書本文の速読で、英語5技能が伸びる理由を説明します。
(1)正しい音を聞いて(ICレコーダー使用)速読すれば、正しく発音された音が習得されるので、定期テストや高校入試での「聞く力」が向上します。
(2)正しい音を聞くので、英語がスムーズに口から出やすくなって「会話力」が向上します。
(3)英単語の拾い読みでは、決して制限時間内に読めないように時間設定をしています。英文を暗記して、一気に読む練習を繰り返し練習して、やっと制限時間内に読むことができような、時間設定です(上位生ほど音読速度が速いことが分かります)。これによって、自然に英文の暗記ができて、「英作力」が向上します。
(4)英文の構造が感覚的にわかるようになるので、「長文読解力」が向上します。
(5)字体の一番大きな英単語があるのは、英語教科書の本文です。町の看板ではないですが、大きい字体は視覚的に印象が強化されるので、「英単語の綴りの暗記」に役立ちます。
このように教科書本文の速読には、「聞く力」「会話力」「英作力」「長文読解力」「英単語の綴りの暗記」の向上という一石五鳥の効果があるのです。
(6)おまけの効果:既習事項の短時間総復習に役に立つ。
例として、中3の new horizon2021年版の本文 unit3 を調べてみます。中1から今までに習った文法事項(冠詞・形容詞・副詞・比較・前置詞・接続詞・動詞の全ての時制型・5文型・受動態など)の9割が出ています。入試直前の既習事項の短時間総復習に最適な教材です。
教科書本文の「時間制限付き(タイマー使用)の速読テスト」では、音読時間と発音の2つのチェックをします。不合格の時は、音読の再学習です。
- ICレコーダーとタイマー
このページのトップに戻る
●3 自学能力を高める徹底した反復指導
生徒が自学できないのは、既習分野の習得が不十分なため。厳選した既習分野を制限時間内にできるまで反復(指導中は、一人一人にタイマーを渡しています)。そうすると、つきっきりで教える必要がなくなり、学校授業もわかってきて成績が上がり始めます。
春期・夏期・冬期の講習では、既習重要事項の反復指導をしてから、応用問題の指導をして、新学期に備えます。
このページのトップに戻る
●4 充実した中間・期末テスト対策
中学校の中間・期末テスト2週間前から、9~15時間の学校教材持ち込み可の無料指導。(下図は、中間・期末テスト10日前に各生徒へ配布する中間・期末テスト対策授業の予約用紙です。各中学校のテスト日に合わせて配布します。)
このページのトップに戻る
- ●5 毎回の指導報告と年2回の定期保護者面談
進級・単元テスト結果、宿題達成状況、出席・遅刻の有無を毎回ご報告。さらに塾長が7月と12月に全生徒の保護者面談をしています。
このページのトップに戻る
●6 低月謝による圧倒的な指導回数・時間数・宿題チェック- ⑴ 一つの教科を週1回指導では伸びません。授業の間が1週間空くと、前回習ったことをスッカリ忘れるからです。ドイツの心理学者エビングハウスは、学習後20分後には、習ったことの42%忘れ、1時間後には56%忘れ、1日後(24時間後)には74%忘れ、1週間後には77%忘れ、1か月後には79%忘れる、というデータを発表しています。…「エビングハウスの忘却曲線」として、暗記法の文献に必ずと言ってよいほど、引用されています(下の図は、工藤紘実著「同時通訳者の英単語暗記メソッド111」,秀和システム,2017年
からの引用です。
業界特有の専門英語を短時間で覚え、ミスが許されない、しかも即答しなければならない、という過酷な職業は「英語の同時通訳者」でしょう。大手企業・官公庁に派遣される同時通訳者が行っている英単語暗記法を紹介した本書は、事実に基づいて、実用的で、指導上とても参考になります。三田市図書館にあります)。 - 注:↑の「2時間後」は書籍の誤りで、正しくは「1時間後」のようです。
- さらに、カナダのウォータールー大学での実験結果では、
・授業内容を復習しない場合、30日後にはほとんどの知識を忘れる。
・授業から24時間以内に、10分の復習をすると、記憶が100%(授業直後の状態)に戻る。
・授業から1週間後に、2回目の復習をすると、5分で記憶を取り戻せる。
・授業から1ヶ月後に、3回目の復習をすると、2~4分で記憶を取り戻せる。
つまり、復習のタイミングは、「24時間以内(または、習ったその日の寝る直前)」「1週間後」「1ヶ月後」…が望ましいのです。それでも完全に覚え切れませんが、この様に3回に分けて復習すれば、難しい学習内容でも長期的な記憶に結びつけられます。
- 以上2つの資料から、一つの教科を週1回指導の生徒は、1週間後の塾のある前日に、77%忘れた状態で慌てて宿題を解くから、誤答だらけの宿題ノートを提出することになります。
脳はどんなことでも反復すれば記憶するので、この時、誤答になる計算方法・発音・漢字を、しっかりと習得したことになるのです。正答率80%以上の宿題でなければ、その宿題は生徒にとって有害です。後で間違った方法を矯正するのに、多くの時間を費やすことになるからです。
⑵ もう一つ大事なことは、「宿題をさせる」の重要性です。どんなにいい授業をして、生徒を完全に分らせても、1日後(24時間後)には74%忘れてしまうのです。だから、いい授業した後の、忘れさせないための類題を宿題に必ず出すことです。
さらに、宿題を出しても、したかどうかをチェックしないと、生徒はしてこなかったり、手抜き(数学の例:途中の式を書かないで、適当な数字を入れてごまかす。)をしてしまいます。そこで、宿題の達成度をチェックするために、下図のような「宿題ノート箱」を設けています。授業中の隙間時間に、宿題ノートをチェックして、宿題達成度を5段階で表し、生徒に返却します。返却後、生徒はすぐに答え合わせをして、分らないところは、講師に質問するようにしています。
成績が伸びる条件は、教え方の上手な「いい先生」と、宿題を必ずしてくる「まじめな生徒」の2つだ、ということです。
最近は、問題集の解答を生徒に渡しています。理由は、これまで、宿題で間違った解法で誤答を量産する生徒がいたからです。この時、問題を解いて、すぐに手元の解答で答え合わせができたら、早く間違いが修正できて、学力アップにつながるはずです。「解答の丸写しをしても、塾で宿題範囲のテストをするので、ばれるぞ」と、くぎを刺しています。
- ⑶ 上記のように、指導・宿題をセットにして、月謝を安くしてでも週2回受講してもらえば、3日空くだけなので、忘れる前に新しい内容を指導でき、成績が上げられます。低月謝(大手個別塾の半額)は「週2回受講=成績アップ」へのこだわりです。
- ⑷ 「問題集は1冊を5回繰り返せ」が指導資料です。いきなりテストをして、80%以上解ければ、より難しい問題集に手を出してもよい、と決めています。「成績が上がらない」といって他の問題集に次々に手を出すと、反復回数が減って自滅します。教材費で儲けようとする大手塾より教材費は少ないけれど、この方がよく伸びます。(ネットで調べると、参考書・問題集は1冊に絞れ…このような、情報が多く発進されています))
- 大手塾では、夏期・冬期などの講習中は、平常授業とは別の「講習専用教材」を使うところがほとんどです(以前大手塾に勤めていました)。当塾では、講習専用教材は一切使いません。平常授業で使う教材には、すでに✕・△・〇で進級テスト結果が記録されています。この個人記録を使って、講習中には✕・△印の単元・項目を重点的に反復指導します。〇印の単元・項目は指導しないで、宿題だけにするか、応用的な内容を指導します。これこそが「伸ばすための個別指導」です。一斉授業よりも優位に立てる武器です。
- ⑸ 個別指導とは「一人一人、別々に指導する」という意味ですが、当塾は、この意味から脱して、一斉指導ではできない、しかも学力向上に有効な「伸ばすための個別指導」を追求しています。
このページのトップに戻る- ●7 志望高と生徒の両方に合わせた「私立・県立高入試対策」。無理・無駄のない「中入試対策試」
- ●当塾の私立・県立高校入試の指導法
高校の合格判定には、2学期末テストまでの内申点が使われます。したがって、このテストまでは学校の試験に合わせます。その一方で、夏期講習から入試対策を始めます。
本格的な受験指導は、12月になってからになります。英語の方は12月初めに終わりますが、数学は、内容が多くて12月末までかかります。ここから本格的に、以下のような入試対策をします。 - ①私立高校(5年間の過去問演習・類題演習)。 ②兵庫県立高校(推薦入試:小論文・作文指導。一般入試:5年間の過去問演習・類題演習)。 ③高専入試(5年間の過去問演習・類題演習)による志望校別受験指導をしています。
過去問演習の結果を生かして、不得意分野だけを指導し、得意分野は宿題に出します。この無駄のない指導が、個別指導が集団指導よりも受験で優位に立てる武器です。
- 県立高対策のために、毎年県下100塾が参加する大手の塾教材専門の出版社「中央教育研究所」主催の「兵庫入試問題分析会」に毎年参加して、入試傾向をつかんでいます。陰山英男氏の「AIの進歩で今の子供たちは将来食べられなくなる、というのはおどしだ。別の欲望が生まれて新しい産業が生まれる」。デーンと構えて基礎学力を徹底反復しろ、と理解しました)。17年入試で英語に満点の生徒が出ました
- ●当塾の三田学園中学入試指導法 (他の中学入試対策は、これをアレンジして対応します)
①学校準拠教材を使って、小6の内容を、小6の4月までに指導します。
②小6の4月以降、受験用教材を使って、中学入試勉強をスタートします。
①②の解説
一斉指導の進学塾の場合、さっさと小6の終わりまで教えて、中学入試対策に進むと、途中入塾の受験生が学校で習っていないことが多くて、入試対策授業について行かれません。このために、学校進度と入試対策を並行しなくてはいけないのです。
このために、一斉指導の進学塾がよく使うハイレベルの教材には、例えば、小5生でも何とか解けそうな入試問題が取り込まれています。
このような入試問題は、本来、小6の指導が完了した生徒に解かせるものです。小6で習う分数の掛け算や比例式を使えばすぐに分かることを、これらの計算が使えない小5生に指導するのは難しいし、時間もかかります。
このように、無理・時間的無駄が多いやり方なので、当塾は学校準拠教材を終えてから、中学入試勉強をスタートします。
③志望中学の出題傾向と難易度に合わせて、出題頻度の高い順に、優先指導します。
④志望中学の過去問(芦研など)を使って、学力の定着具合を確認しながら、出題傾向と難易度の照準を高めていきます。
⑤個別指導では、他の生徒の影響を受けません。上記の当塾の指導法に沿って、合格へひたすら指導します。
参考:一般的な一斉指導の進学塾の指導方法
途中入塾した受験生が、受験コースの授業についていくのは大変です。進学塾の講師時代、「皆について行かれるように補習しますから大丈夫です」と説明しますが、「補習してついて行かれるほど、レベルの低い指導なのか ?」と突っ込まれたらどうしょうか、とドキドキしたものでした。
夏期・冬期講習では、内部生も外部生も同じ教材を買わせて、指導します。同じ教材でないと、一斉指導できませんから。(ネットなどでは、受験指導のベテラン講師は、必ずと言ってよいほど「1冊の教材の反復学習」を勧めています(「参考書・問題集・何冊・勉強方法」で、ネット検索)。これに反する指導方法です)
このように、学校と塾との進度差・生徒間の学力差があり、一斉指導の進学塾には問題が多いのです。多額の広告で優秀な生徒を集めて、合格実績を上げて、このような問題を何とか覆い隠していますが、皆さんはどう思われますか。
- 2024,10,29 「中央教育研究所」主催のセミナー「Educational Network Journal 24年度 兵庫県公立高校入試分析」に参加しました。コロナにより、たびたび延期されたセミナーですが、最近の教育改革に対応した新傾向の問題を察知したいと、多くの塾が参加していました。資料を持ち帰って、分析し、早速、公庫受験指導に反映させたいと思っています。
講師の向井さんは、全国の公立高校入試問題を全部自力で解かれ、レポートされています。その的確な指摘に、すっかりファンになり、2016年から、招待状があれば欠かさず出席しています。
入試傾向に合わせて、塾用教材を出版・販売する出版社としては、当然のセミナーですが、大手塾でも、ここまでのレポートは出せないでしょう。近年は、このようなセミナーやインターネット情報を集めれば、大手塾と中・小塾との情報格差はほとんどありません。

このページのトップに戻る
- ●8 電子教育書籍を多数著作の指導経験豊かな塾長
神戸大大学院工学修士。在学中は何々学園など大手進学塾で教えていました。
国家試験:騒音関係・大気関係第1種・水質関係第1種公害防止管理者、第3種電気主任技術者、宅地建物取引主任者、民間試験:漢検2級、英検2級を取得しています。このような試験を多数受けることにより、受験のコツ(受験計画のたて方、参考書・問題集の選び方、出題傾向の調べ方)を体得しました。
この経験から言えば、合格基準点の2割増しを狙うのが、効率の良い受験勉強です。例えば、100点満点で合格基準点が60点の時、60×2割増し=72点を目標にすることです。別の言い方をすれば、受験のコツとは「基本・標準問題は全問正解にする。難問は一部だけ解く」です。一見、難問に見える問題でも、基本・標準問題の解法を駆使すれば、解ける問題が少しあります。
人はだれでも、基本・標準問題をおろそかにして、難問に手を出しがちです。それを戒めながら、受験指導をしています。
もう一つ大事なことは、必ず時間を計って、過去問をすることです。
その後、川西市の大手塾に勤めました。「こんな指導法では伸ばせない」と三田で独立しました。「大手塾に対抗するには個別指導しかない」と、個別指導法の開発に着手しました。安価で良質の個別指導法は「困難だ」と、当時は言われていました。「教育学部出身者には無理かもしれないが、研究開発(主観的ではなく、客観的なデータに基づいて、指導法を開発すること)が得意な工学部出身者なら出来るかも…」という思い込みで、挑戦しました。そして、今日に至ります。
- 川西市の大手塾に勤務以降40年間一度も欠勤はありません(…と言いたいところですが、2022年11月、コロナ感染で止む無く1週間休塾をしました)。生徒に「勉強は毎日の積み重ねが大切だ」と言いながら、講師の自分が欠勤するわけにはいきません。
自分の学力を高めるよりも生徒の学力を高めることが大事なので、指導法の研究に注力しました。生徒の学力を高めるための電子教育書籍7冊執筆しました。
以前は高校生に物理を教えていました。中学生には英数理を教えていました。卒塾生には、理工系に進む生徒が多いです。
- 塾長の生徒への思い
- 2023年、厚労省の調査では、働く若者の3割以上が非正規雇用です。さらに、新聞やネットでは、「10年〜20年後にはAIによって49%の仕事がなくなる」、「 AI(人工知能)の発達で格差社会拡大の恐れ」、「 会社員の40%が「職を失うことへの不安」を感じている」などの情報があふれています。
- これからは、塾もAIに負けてはいられません。同様に塾生に、社会に出た時に、AIに負けない能力を付加しなくてはいけません。その能力とは、科学技術の進歩により、変化の速い社会で働くための「生涯学習能力」でしょう。
年をとっても、意欲を持って働く私自身の後ろ姿を、何気なく、そっと、脳裏に焼き付けたいとの思いで、日々、生徒指導を続けています。「だてに、年は取っていないぞ」です。 - 塾長の出版への2つの思い
中学理科「電気」の指導法に取り組んでいます。
以前、公的なアンケート調査で、「電気は中学生にとって最も苦手な理科分野」との報告がありました。
今後とも電気産業は日本の発展に欠かせない産業です。「その入り口の中学理科で、苦手意識を持たせる訳にはいかない。教育学部出身者には無理かもしれないが、研究開発が得意な工学部出身者なら出来るかも…」という思い込みで、挑戦し、従来の「水流モデル」に代わる「自販機・ランナーモデル」を提案しました。このモデルで指導したところ、「分った」と塾生が言ってくれます。
英語の学習を受動的に、仕方が無くやっている生徒がほとんどです。「仕方が無く」の勉強ではなく、世界に打って出るためのビジネス手段として英語学習に取り組んでほしい」という2つ目の思いと同時に、「おそらく苦手意識を持つのは、外国の中学生も同じだろう…」ということで、英語版「オームの法則」も出版しました。
ー2025,03,20に、この場所に掲載していた人物写真を削除しました。ネット上での悪用を防止するためです。ー- ◎ 学院長の電子書籍の紹介…内容は『書名』でご検索
- ①『どの子も伸ばせる指導法』楽天kobo、グーグルブックス 2011年
1995年ごろ、相野教室・志手原教室・南が丘教室・藤原台教室と展開していました。しかし、阪神・淡路大震災で南が丘教室のみを残して他の教室は閉鎖しました。この結果、講師の研修に多くの時間を費やす必要がなくなり、個別指導法の「本でも出そうか」と、取り組んだのがこの本です。内容は、ページトップのメニュー「学力差・集団指導・個別指導の研究」をご覧ください。
- ②『省エネ式 年代暗記』でじたる書房 2011年
- 歴史上の事件・出来事の、楽な年代暗記法を書いています。地理・公民と違って、歴史は暗記事項が多く、生徒はうんざりしています。何とか暗記の負担を軽減したいとの思いで、書きました。
- ●工夫の1つ目は、「年号→事件」型の問題にしぼった暗記法。
毎年、中学・高校入試に出されるのは「年号から起こった事件を答える」型の問題ばかりです。この順にゴロ合わせ文も合わせています。
例、593年 → 聖徳太子が摂政となる。
ゴロ合わせ文「コックさん 特大コショウを 振りかける。」
●2つ目は、1001~1899年に起こった事件は1000を省略。
例、1543年 → ポルトガル人が鉄砲を伝える。
ゴロ合わせ文「腰から下げる刀より 鉄砲。」
543年というのは、聖徳太子が活躍する少し前の時代です。この時代に、ポルトガル人によって鉄砲が日本に伝えられた、とはとても考えられません。1000を省略している、とすぐにわかるからです。これで事件の多い1000年代が、簡単に覚えられます。
●3つ目は、1901~1999年に起こった事件は1900を省略。
例、1941年 → ハワイの真珠湾を攻撃、太平洋戦争おこる。
ゴロ合わせ文「よい 真珠。」
1841年というのは、江戸時代です。この時代に、日本が飛行機でハワイの真珠湾を攻撃して太平洋戦争おこる、とはとても考えられません。1900を省略しているとわかります。これで事件が頻発している1900年代が、とても簡単に覚えられます。
以上3つの工夫により、従来の4桁年暗記法に比べ、大幅な暗記エネルギーの節約になるので、「省エネ式」と名づけました。
③『2と6に置き換えて解く 小学4・5・6年算数文章題』でじたる書房 2011年- 小4の割り算文章題例:「28本のかんジュースを、2本袋に入れます。2本入りのふくろは何ふくろできますか。」
- このような問題を多く解くうちに、たいていの児童は、「大きな数を小さい数で割れば、問題を読まなくても答えが出る」と気づきます。しかし、小5になると「2.8Lのジュースを、4つのふくろに等分します。1つのふくろは何Lになりますか。」のような、小さい数を大きな数で割る文章題が出てきます。ここで多くの生徒が「大きな数を小さい数で割れば、問題を読まなくても答えが出る」という小4での癖が出てしまって、つまずくのです。問題の意味を理解して解く必要が出てくるのです。
この壁を乗り越える指導法を述べた本です。
- ④『自動販売機・旅人モデルによる 中学電気計算』でじたる書房 2011年
- 中学理科「電気」の指導法に取り組んでいます。以前、公的なアンケート調査で、「電気は中学生にとって最も苦手な理科分野」との報告がありました。今後とも電気産業は日本の発展に欠かせない産業です。「その入り口の中学理科で、苦手意識を持たせる訳にはいかない。教育学部出身者には無理かもしれないが、研究開発が得意な工学部出身者なら出来るかも…」という思い込みで、挑戦し、従来の「水流モデル」に代わる「自販機・ランナーモデル」を提案しました。このモデルで指導したところ、「分った」と塾生が言ってくれます。
英語の学習を受動的に、仕方が無くやっている生徒がほとんどです。「仕方が無く」の勉強ではなく、世界に打って出るためのビジネス手段として英語学習に取り組んでほしい」という2つ目の思いと同時に、「おそらく苦手意識を持つのは、外国の中学生も同じだろう…」ということで、英語版「オームの法則」も出版しました。youtube動画も発信しました。
- ⑤『自販機・ランナーモデルによる 中学受験電気計算』でじたる書房 2015年
- ⑥『自販機・ランナーモデルによる 高校受験電気計算』でじたる書房 2015年
⑦「教えるのが楽しくなる新『オームの法則』指導法」 アマゾンKDP 2020年 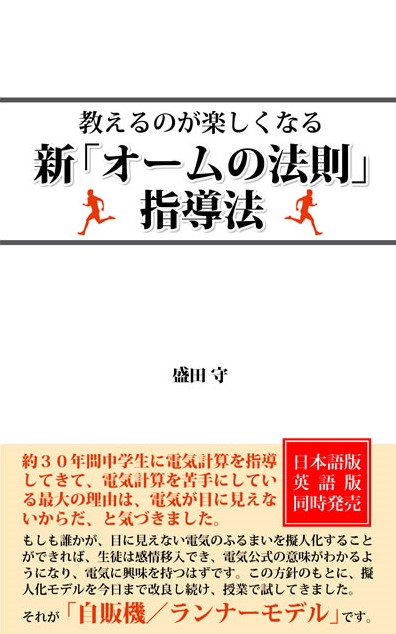 ⑧「New "Ohm's Law" Teaching Method」 アマゾンKDP (Kindle Direct Publishing)2020年 本書は⑦の英語版です。米国・ヨーロッパで発売中。
⑧「New "Ohm's Law" Teaching Method」 アマゾンKDP (Kindle Direct Publishing)2020年 本書は⑦の英語版です。米国・ヨーロッパで発売中。
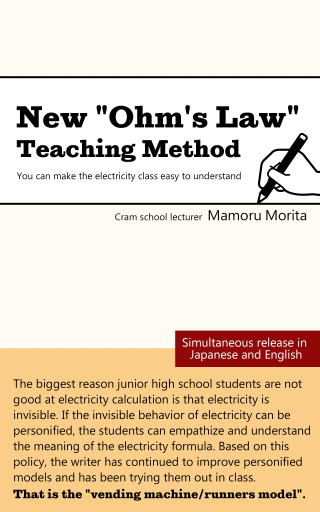
- いずれの本も、生徒指導の現場から編み出した指導法を提案しています。
拙著が電子書籍のベストセラーの上位を占めました。 2018,5,25現在
2.位 『自販機・ランナーモデルによる高校受験電気計算』でじたる書房 著者 盛田守
3.位 『自販機・ランナーモデルによる中学受験電気計算』でじたる書房
4.位 『自動販売機・旅人モデルによる中学電気計算 』でじたる書房 -
- 塾長のYouTubeのご案内 下線文字をクリックされると動画視聴できます。
①『中学電磁気 新ゴロ楽々速習』全5章 - 1章 棒磁石とU字型磁石の磁力線 https://youtu.be/e2qL4fKoui0
2章 直線電流が作る磁界 https://youtu.be/gW_nIUmBxAU
3章 コイルの電流によって発生する磁界 https://youtu.be/K-KML5W489w
4章 直線電流が磁界から受ける力(左手則) https://youtu.be/KUn6U4w4QSU
5章 電磁誘導(発電機の原理) https://youtu.be/i9ok1wm8dPM
②「中学電気計算 新モデルで楽々速習」全5章 - 1章 モデルの紹介/オームの法則(抵抗の直列回路) https://youtu.be/_2ANhB6Kv-E
2章 「自販機・ランナーモデル」の約束事 https://youtu.be/a1dqD5L7_ZU
3章 抵抗 https://youtu.be/C0RVnP3UsVU
4章0 オームの法則と覚え方 https://youtu.be/EkmDKrSjroo
4章1,2 オームの法則(抵抗の並列回路) https://youtu.be/BASiJmQhr5M
5章 電力 /6章 電力量 https://youtu.be/VuhUHKdSRLI
- このページのトップに戻る
- ●9 理系コース新設 ! 将来を定めた指導へ ! (下剋上コースに名称変更)
- 厚労省の調査では、働く若者の3割以上が非正規雇用です。その特徴は①「所得が低くなる」②「雇用が不安定」③「専門的な能力が磨けない」です。特に③の「専門的な能力が磨けない」と、いつまでたっても単純労働を強いられて、非正規雇用から抜け出せません。習得すべき能力は、機械化・自動化・AIを担うITエンジニア、そして患者の顔色から体調の変化に気付いたりするなど、ロボットに置き換えられない仕事を担う看護師などの理系の知識です。時代の変化が速いので小中生から理系指導を進めます。
英数理3教科セット指導。個別の実験や関学理学・工学部・公立高校の科学イベントなどの引率により好奇心を育てます。
北三・祥雲・高専を目標。宿題量は進学塾と同程度で、レベルは個別対応。 - このページのトップに戻る
●10 学習障がい生の指導- 1 学習障がいの3つのタイプと指導法
-
種類 特徴:よく見られるつまずきや困難の一例 当塾の指導法 読字障がい 文字を間違って発音する。読むのが遅い。よく似た文字の区別ができない(あ。お、ぬ・め、の・め、 q・d、b・p、w・mなど)。文章の音読はできるが、意味が理解できない。 集める、焦げるは、木を集める、火(れっ火)で焦げると覚えさせる。部首から漢字の意味を覚えさせる。漢字の学習漫画を使う。
bもビも縦線の右に、dもデも左側に伸びていると教える。
音読を3回させる。タイマーで計って、速読を促し、時々テストをして、少しずつ速く、正確に読めるようになっていることを実感させて、やる気にさせる。書字障がい マス目の大きさに合わせて書くことが苦手。行を揃えて
書けない。平仮名や漢字の細かい部分を間違って書く。
漢字の“へん"と“つくり"を間違える。
単語に誤った文字が混じる1回に解く問題の数を減らし、じっくりていねいに書かせる。
大きいマスの方眼ノートを使う。
漢字の学習漫画を使う。計算
障がい計算の手順が分からない。数字や位取りを揃えて計算できない。数字の位どりが理解できない、繰り上がり、繰り下がりが理解できない。九九がなかかな覚えられなかったり、唱えられない。暗算ができないか、遅い。ケアレスミスが多い。 図解やイラスト入りの学研「一つ一つ分かりやすく」シリーズを使う。
頻繁に反復させる。指導のステップを細かくし、十分な演習問題をさせる。タイマーを使って計算速度を計る。遅い場合は間違った解き方をしていることが多い。成績が上がったらほめる。紛らわしい数字はケアレスミスにつながるので、即、直させる。放置すると後で修正できなくなる。立体は、立体模型を使って説明する。 - 2 当塾の指導経験
1,小6 A子さん
34-17= のような繰り下がりがある引き算が苦手。年少~小3レベル用の図解入りの教材を使って指導。結果は、6か月ほどして、やっとできるようになって、次のステップの計算を指導。1週間ほどして、念のために繰り下がりがある引き算をさせたところ、解けなかった。6か月の指導は、何だったのか。保護者が「何をしても、できないのが分かった」と、学研教室にご転塾。計算障がいで「数字の位どりが理解できない、繰り上がり、繰り下がりが理解できない」に該当します。
2、中1 B子さん
20年前のことです。千円札2枚で千2円と答える。位取りが理解できない。千円札カードを大量に作って説明したが効果なし。 - 一方、漢字の読みができたので、漢検の5級(小学6年生修了レベル)を指導して、合格。お母さんがたいそうお喜びでした。「数学もお願いします」と言われた時には、絶句しました。位取りが理解できないのに、伸ばしようがありません。成果を上げると、より一層の成果を要求されるのです。たまったもんではありません。ご退塾。
計算障がいで「数字の位どりが理解できない」に該当します。
3,小6 C君
計算力は小3レベル。小6の計算は教えられないので、なんとか対称図形などの図形を指導。しかし、分数を教えようとしても、頭を抱えて、拒否。「計算は苦痛以外の何物でもない」との態度。考えても分らないものは、すぐに拒否。そのうち、机に突っ伏して寝る。他の生徒に迷惑がかかるので、塾の規約に基づいて、退塾をお願いしました。発育障がいと学習障がいに該当。
4,中1 D君
初めての受講日、夜10時ごろ送迎車でご自宅まで送りました。翌日お母さんから、「うちの子が自宅まで道案内しましたか」と、声を弾ませて、ご質問。「いえ、住宅地図を見ました」。「そうですか」と少し落ち込んでいました。
どうやら、自分の思っていること、言わないといけないことがしゃべれないタイプのようです。学校でよくいじめられるとおっしゃっていました。
そのような生徒でも、「説明→問題演習→確認テスト→×の説明」の当塾の指導法であれば、分からないまま進むことがないので、安心して入塾されたのでしょう。中1,2,3年と進むにつれて、学習内容が難しくなって、学習意欲を失っていきました。
保護者面談の時「それは仕方がない」と言われました。障がいを持つ子の指導の困難さをよくご存じのようで、助かりました。兵庫県立上野ケ原特別支援学校にご進学。発育障がいに該当。
5,中2 E君
「うちの子には障がいがある」と、「WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)知能検査」をご持参されました。その子の興味を持つ方向にお育てになったようです。小学生の時からプログラミング教室に通われていました。将来はプログラミング関係の仕事に、とお考えでした。数学は文章題が解けなかった。知能検査の総合所見の指摘通り、教科書の絵や写真をつかって説明するようにしました。兵庫県立尼崎工業高等学校に進学されました。軽度の学習障がいに該当。
6,中3 F君
中3の三平方の応用問題で、立体図形が「全然わからない」と言われてびっくり。「小さいときに、ジャングルジムで遊ばなかったのか」と質問しました。急いで、クリアーホルダーをカットして、立方体、円錐、角錐、円柱の模型を作って指導。今度は、自分で作って、それを見ながら宿題を解くように指示。北三合格。岡山大学現役合格。こんなによくできる生徒の中にも、局所的な学習障がい生がいるのです。おそらく、進学塾のトップクラスの中にも、このような生徒がいるのでしょう。
以上のような結果です。「学習障がい」というだけあって、学習指導は困難を極めます。ひとりひとり症状が違い、それに対応して、教材を作っても、効果が上がることはまずありません。なんとか改良して使えるようになっても、その教材は他の生徒には使えません。教材費がどうしても高額になります。
中学校の中間・期末テストに、学習障がい生用のテストはないのです。みんな一律のテストです。このテストが解けるように、小学2年生に戻ってやっと掛け算九九が使えるようになったような学習障がい生を指導することは不可能です。
成果が上がれば、堂々と教材費や月謝を上げられるのでしょうが、無駄になった教材で赤字の山です。疲れます。「学校の平均レベルに伸ばしてほしい」とのご希望は、達成困難です。どの塾でも同じだと思います。
3 当塾の学習障がい生の受け入れ条件- ① WISC―Ⅳ(ウイッスク・フォー)検査を受けて下さい。指導方針、教材の準備がやりやすくなります。医療機関の方の説明で、学習障害の実態をご認識していただけます。これにより、塾に対する過剰な要求が防げます。
② 「学校の平均レベルまで伸ばしてほしい」とのご要望は達成困難です。どんどん進む学校の進度に、2・3年も遅れている生徒が追いつくのは、不可能です。 - ●11 効率的な学習法の指導
- 1つの会社・1つの職業で、一生を終えられる時代は過ぎました。これからの時代は、常に自分を進化させながら生きていかなければ「飯が食えません」。子供たちが、将来自分を進化させるときに必要な、次のような効率的な学習方法を指導します。
- ①反復と反復の時間間隔 ②音読の有用性 ③1週間の学習計画の立て方 ④暗記技術 ⑤問題集の効果的な使い方
特に④暗記技術には力を入れています。どんなに分かりやすく教えても、次回、何も暗記していなかったら、0点ですから。
暗記技術の指導例
⑴「問 次の数から、自然数を選びなさい」 自然数の意味が分からないと解けないです。
自の文字の上に1が乗っています。これに注目して、1,2,3,・・・を自然数と呼ぶ。字体の中に記憶のヒントを見つける方法です。- ⑵「問 示準化石とはどんな化石ですか」の暗記法。
示準化石の準の字体には、十が含まれています。これは t と読めます。timeを連想して、新生代などの時代が分かる化石だと記憶します。「僕なら、準から 時代の順番を連想する」と、生徒から別の優れた暗記法を教えてくれました。
⑶「問 長野県の主要な農産物を答えなさい」
長の字体の中に レ があります。レタス・白菜・キャベツの高冷地野菜が暗記出来ます。
- ⑷「問 山形県の主要な農作物を答えなさい」
形ガタ と音がする。おうとう(サクランボ)。 似たような音声を利用する記憶法です。 - ⑸「島根県、香川県、愛媛県の県庁所在地名が覚えられない」という中3生がいました。
左から順に、松江、高松、松山が答です。全ての都市に「松」が含まれています。語呂合わせが難しいケースです。
中国地方・四国地方の地図の上に三角形を書いて、頂点が松江、右下の頂点が高松、左下が松山。時計回りに「エー玉 投げろ」で、覚えてもらいました。 - 他にも、数学公式、理科公式、英単語の暗記法を、生徒と競っています。
せっかくの暗記法を教えても、暗記できない生徒がいます。その時は、2分間で30回音読を勧めます。
●12 英単語の暗記指導法
① フォニックス(英語の発音と文字のルール)を、中学3年間に渡って指導
例えば、大阪、神戸という漢字をしっかり覚えて、日本観光に来たアメリカ人がいたとします。阪神電車に乗りたいと「阪神(さかこう)電車はどこですか」と聞くようなものです。阪にはサカ・ハン、神にはコウ・シンの2通りの読み方があることを知らないと、困るでしょう。同様に、ローマ字読みを習得しただけで、英語に入ると、絶対に困ります。英語嫌いになります。さらに、悪いことに、2021年4月新学習指導要領により、中学3年間で扱う英単語が約1.5倍、1,200語から約1,600~1,800語に急増しました。さらに改定で、2500語になり、大学受験並みの語数です - 英語の基礎は、絶対フォニックスです。これがグラつくと、英語は伸びません。音読ができないからです。フォニックスは絶対に忘れてはいけないルールなので、中学3年間に渡って、繰り返し指導します。すぐには覚えきれないので、頻繁に繰り返し暗記させます。暗記テストをして、✕ は次回再テストをして、90パーセントの正答率を維持するようにしています。中3で、いきなりのテストで、90%暗記できている生徒は北三に合格しています。
- 指導例
例1:ooはウ、ウーの2つの発音があります。ウ:book、woody。ウー:food。
例2:oはオ、オウ、アの3つの発音があります。オ:boy。オウ:open。ア:woody town. 三田でよく耳にする単語を使って、指導するようにしています。
この調子でaからzまでを、また、これら以外では頻出のルールを指導しています。この結果、英単語の綴りを見れば発音が予測できるようになります。
②発音について- 2012年にHarvard Business Review から発行された記事「世界 人口 の内約17.5億人が 英語話者 で、その約78%(5人に4人)が非ネイティブ(英語を話す国に生まれていない人)」について思うこと(https://youblog.world/) からの引用です。
- あなたが将来英語で会話する相手は、高確率で非ネイティブ。発音は、正しさよりも相手が理解できるかが大事。発音の違いはあなたの個性になる。英語の発音や話すことが苦手でコンプレックスを持っている人も多いと思いますが、英語という言語は、いろんな人たちに使われ最もフレキシブルな言語ですので、劣等感を感じる必要もないし、不安になる必要もないので、旅行でも留学でも海外就職でも思い切って海外に飛び出してみてはどうでしょうか。(引用終わり)
- これを読むと、発音にそれほど神経質になる必要はないようです。神経質になると、発音学習のために学習エネルギーを費やすことになり、かえって、英単語の暗記数が減ります。当塾はこの方針に切り替えました。
- ③ 派生語(語根の一部・接頭辞・接尾辞)を、中学3年間に渡って指導
指導例 - use(使用する)を知れば、useful(使用できる→形容詞:役に立つ),usefully(副詞:役に立つ用に),useless(形容詞:使用出来ない→無駄な),uselessly(副詞:むだに),user(使用する人),misuse(使用する),reuse(再使用する)。
このように、英単語の暗記量を一気に増やすことができます。ただし、接頭辞・接尾辞は無数にあります。そこで、中1・2・3年のホライズン英語教科書に出てくる全単語を調べ、最重要なものを選んで指導しています。
派生語は絶対に忘れてはいけないルールなので、中学3年間に渡って、繰り返し指導します。すぐには覚えきれないので、頻繁に繰り返し暗記させます。
④ その他の覚え方の指導例
⑴ soon スーン「すぐに」「即座に」「そのうち」「もう少し後」。複数の日本語訳があるときは、1つだけ選びます。スーンの発音を含む「すぐに」が最適な暗記語です。 - ⑵ here,there,where いずれも、hereが含まれ、場所に関係した単語だとして、まとめて暗記させます。
⑶ air,hair 空気の流れに髪が揺れている光景を浮かべて、2語同時に暗記させます。
⑷ catch cat 猫を捕まえる、と暗記させます。同じような発音の単語を並べて、かつイメージしやすいように組み合わせます。文法上は catch cats ですが、単語の暗記を優先して、冠詞などは省略します。 - HP閲覧感謝値引きコード「hoku250802」
ご受講願書にこのコードを、ご記入いただくと、最初の1か月分の月謝または講習受講費を500円割引いたします。有効期限25、08、02まで。 - このページのトップに戻る